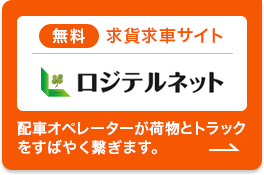こちら🥟ロジテル本社🥟現場の伊藤(大)です👲
いや~~~~~それにしても最近暑いですよね💦
みなさまも体調など崩さないようご自愛くださいね
さて、最近水面下で盛り上がりつつある界隈を
みなさん知っていますでしょうか❓
そうです、、、
⛄冷やし担々麵界隈🐧
※宇都宮市西川田町513−3 あら川さんより
です👲
通常の担々麵であれば
あっつあつで辛さでヒーヒーして汗を掻きながら😥
食べるものですが
意外にゃ意外で、、、
冷やすことで清涼感が出まして
それがなんとも山椒とベストマッチするんです🍜✨
担々麵を冷やす、、、、、
悪魔的でもある コペルニクス的発想の転換
人類の【食】に関する探求の旅路は
まだまだ終わることはないようですね。。。。。
話は変わりますが
最近のマイブームとして
社内の人間にクイズやなぞなぞを出すことに
ハマっております
デスクが近いこともあり
よく野澤社員に出しているのですが
野澤社員の回答に毎日驚かされております
今回はその一部をご紹介させていただきます。。。
第1問
我々ロジテルの大切な商売道具である【電話】を発明したのは誰でしょう❓
①エジソン
②ニコラ・テスラ
③ベル
正解は、、、、、、、、
③ベル
※こちら所説あります
なのですが
野澤社員が出した答えはなんと
野澤社員<。。。。。。。わかりません。
だけど、、、
僕はベルであって欲しいです🥺
!!!
野澤社員は強く そう願ったのです
クイズを出されて 答えるわけでもなく
願う
これには一本取られました🤓
第2問
4人ずつ2組に分かれ、馬に乗ってボールを相手のゴールに入れるスポーツを何というでしょう?
選択肢なしの難問ですが
野澤社員の趣味は競馬観戦🐴
つまり野澤社員の土俵に
寄せたクイズなんで
これはカッコよく答えてくれることでしょう🥳
ちなみに答えは
ラルフローレンのロゴにもなっている
【ポロ】です
野澤社員の眉間にはシワが寄り
険しい表情を浮かべたあと
そっとその口を開いて言いました、、、
みなさんは野澤社員がなんと言ったと思いますか❓
それではいきます。。。
野澤社員<あぶないからやめたほうがいいですよ
・・・・・・・・・・・・・・・
たし🦀
私は思いました
全く野澤社員の言う通りで
馬に乗ってボールを相手のゴールに入れるスポーツは
人間にとってはもちろん
馬を愛する野澤社員にとっては馬に対しても
危険過ぎるんです
今回の野澤社員の回答は
正解を答えるわけではなく
【警鐘を鳴らす】
でした
ということで、、、、、、、、
最後に前回同様チャットGPTが考えた
笑いあり、涙ありで最後に
とんでもないどんでん返しがある
【冷やし担々麵】と【電話】と【馬】を題材にした小説
で締めさせていただこうと思います
【冷やし担々、鳴りやまぬ午後】
第一章 担々亭にて冷やし始まる
宇都宮駅から少し離れた路地裏に、知る人ぞ知る中華料理店がある。
その名も──「担々亭(たんたんてい)」。
老舗とは言っても、外観は年季の入った木造平屋、のれんは日に焼けて色が褪せ、提灯には「中」だけ残って「華料理」の文字が剥げ落ちていた。
だが、それでも毎年夏になると、ある一品を求めて人々が行列を作った。
その一品とは──
「冷やし担々麵」。
「冷やし中華じゃないの?」「坦々麵なのに冷やすの?」と、よく言われる。
だが、一口食べればわかる。
普通の坦々麵とはまるで違う。冷たい胡麻の風味とピリッと効いた辣油、そして特製の冷製肉味噌とモチモチの中太麵。まさに“夏限定の奇跡”とまで言われた逸品だった。
だが、今年もそのメニューは貼られていなかった。
張り紙には、手書きの丸文字でこう書かれている。
「今年も冷やしはやりません。担々亭 店主」
厨房の奥で、**馬場信吾(ばば・しんご)**は、顔中汗まみれになりながらチャーハンを振っていた。
55歳。坊主頭に鉢巻き、Tシャツには油と汗の染みが広がっている。
「親父の冷やしを出すのは、もう俺には無理だっての……」
客が冷やし担々麵の有無を訊いてくるたび、信吾は決まり文句のようにそう答えていた。
事実、信吾の父・馬場善三(ぜんぞう)は、“冷やし担々麵の生みの親”だった。
地元テレビや雑誌にも取り上げられ、全国からファンが訪れるほどだった。
──だが、昨年。
善三は、突然倒れて帰らぬ人となった。
その日を境に、信吾は「冷やし担々麵」を封印したのだった。
父の死をきっかけに、信吾は冷やし担々麵のレシピ帳を一切開かなかった。
厨房の奥の戸棚に、父の手書きノートが眠っていることは知っている。
そこには細かい分量のメモ、出汁の取り方、胡麻ペーストの作り方、そして何より──「あの冷たさ」をどう生むかの秘密が書かれているはずだった。
だが、信吾は見なかった。
見れば、作れと言われる気がしたから。
そして──作れたとしても、父の味には絶対に届かないと、自分でもわかっていた。
「はぁ……また断っちまったな……」
昼の営業が終わり、信吾は厨房の端で麦茶を飲みながら、カウンターをぼんやり眺めていた。
扇風機の風が生ぬるく、流れる汗をまるで慰めてくれなかった。
そのときだった。
プルルルル…… プルルルル……
黒電話が鳴った。
担々亭のカウンターに置かれた黒電話は、店が開業した昭和40年から使われている年季物だ。
今どき、スマホで注文する時代に黒電話なんて……と笑われることもあるが、信吾はこの電話だけは捨てられなかった。
ガチャリ
「はい、担々亭です」
「……あの、冷やし担々麵、やってますか?」
一瞬、時間が止まった気がした。
若い女性の声。
ややハスキーで、語尾にかすかな震えがある。
「……やってません。すみません、去年で終わりまして」
「……そうですか……やっぱり」
声がふっと沈んだ。
そのトーンに、信吾は思わず尋ねた。
「……前にも来られました?」
「……昔、一度だけ。まだお父さんが厨房にいた頃。母と一緒に。……でも、その時、母はもう……」
「ん?」
「いえ、なんでもないです。……失礼しました」
プツッ。
通話は突然、切られた。
しばらく、信吾は動けなかった。
湯気の残る厨房の中で、冷たい汗が背中を伝う。
(……母と一緒にって……)
どこかで聞いたことがあるような声。
そして、その“母”という言葉に、わずかに心が引っかかった。
その夜。
閉店後の店内で、一人黒電話を見つめながら、信吾はつぶやいた。
「まさかな……あれが“あの子”ってわけじゃ……」
まさか。
でも、声は……どこかで確かに聞いた覚えがあった。
父の遺影が、壁の上で静かに微笑んでいた。
翌朝、店を開ける前。
信吾は、ふと厨房の奥──普段は開けない戸棚の前に立っていた。
(……見るだけ、だ)
そう自分に言い訳しながら、ガチャンと錆びた取っ手を引くと、奥から一冊の黒ずんだノートが現れた。
それは父・善三が使っていたレシピ帳だった。
表紙には油染みや火の粉で焦げた跡があり、「担々ノ型 冷専用」とだけ、丸い文字で書かれていた。
「……これだよ、親父」
恐る恐るページをめくる。
そこには、細かすぎる調味料の分量と、温度、湿度、季節ごとの茹で時間の違いなど、異常なまでに細かく書かれていた。
中でも、ある一行が目に留まった。
“冷たさは、心で作る。驚かせるな。包みこめ”
「……詩人かよ」
思わず笑ってしまった。
父らしい。料理は科学ではなく、生き物だと、いつも言っていた。
ふと、ページの間から一枚の古い写真が滑り落ちた。
白黒のその写真には、若き日の父と、笑顔の女性、そして──一頭の馬が写っていた。
(……え? 馬?)
「なにこれ、サラブレッド……か?」
なぜ料理ノートに馬の写真が挟まっているのか。
意味がわからなかった。
しかし、その馬の隣に立つ若き父の表情が、妙に誇らしげで、嬉しそうだった。
そのとき──
プルルルル…… プルルルル……
またしても、黒電話が鳴った。
信吾は一瞬、躊躇した。
けれど意を決して受話器を取る。
「はい、担々亭です──」
「……今日は、お店、開いてますか?」
「えっ……あ、はい。11時半からやってますが」
「……行っても、いいですか?」
女性の声。昨日と同じだ。
電話の向こうで、微かに風鈴のような音が鳴っていた。
「もちろん。冷やしはないけど、担々はありますんで」
「……それでいいんです。じゃあ……後で」
またしても、すぐに通話は切られた。
信吾は受話器を置いたあと、レシピ帳をゆっくり閉じて、深く息を吐いた。
「来る、のか……あの子が」
冷やし担々麵を通して始まった、不思議な再会。
だがこの時の信吾はまだ知らなかった。
このあと自分が、「馬」「電話」「担々麵」、そして失われた家族の真実へと巻き込まれていくことになることを──。
第二章 ミヅキ、風のように現る
昼の営業が始まる直前、担々亭の前に一人の女性が立っていた。
陽光を和らげるためにかぶったツバ広の帽子、肩まで流れる黒髪、透けるように白い肌。
だがそれよりも印象的だったのは、彼女の目だった。
どこか懐かしく、深い悲しみを湛えたような、真っ直ぐな黒い瞳。
信吾は暖簾を上げた瞬間、彼女と目が合った。
「……あなたが、担々亭の方ですか?」
「あ、はい。どうも……」
「……やっぱり。声、同じだったから」
「……え?」
彼女は微笑んだ。
だが、その笑顔の裏には、どこか影があった。
「ミヅキ、と言います。……この店、昔、母に連れてきてもらったことがあるんです。冷やし担々麵、食べに」
「ああ……その、電話の……」
「はい。昨日、かけたの、私です」
ミヅキは中に入り、カウンターの端に腰掛けた。
昼前の店内は誰もおらず、厨房の換気扇が回る音だけが静かに響いていた。
「残念だけど……冷やしは、もうやってなくてね」
「ううん、いいんです。温かい担々麵でも」
信吾は、どこか落ち着かない気持ちで、鍋に火をつけた。
「母がね……最後に食べたがってたんです。冷やし担々麵。……たぶん、あなたのお父さんが作ったやつ」
「……そうだったんですか」
「母は末期がんで……食事ができなくなってからも、口癖みたいに言ってた。“もう一度あの冷たい担々麵が食べたい”って」
信吾は、手を止めた。
「……その時、あなたはいくつだったんですか?」
「十歳でした。まだ味なんてよくわかってなかったけど……あのとき、母が涙を流して喜んでたの、覚えてて」
鍋の中のスープが、グツリと小さく沸いた。
「……親父、そんな顔をさせてたんだな……」
「え?」
「いや、なんでもない。……今、作ります。熱いけど、気に入ってくれるといいけどな」
ミヅキは静かにうなずいた。
十数分後。
目の前に湯気を立てる担々麵が置かれる。
ミヅキは一口すすると、目を見開いた。
「……似てる。でも、違う」
「やっぱ、俺のは違うか……」
「ううん。全然悪い意味じゃないんです。ただ、……あなたの味です、これ。あたたかくて、辛いけど、やさしい」
その言葉に、信吾は一瞬言葉を失った。
「……なんか、ホッとしたよ」
「でも……いつか、あの冷やし担々麵を、また……」
「……ああ、そうだな……」
言いながらも、心のどこかに、冷たい重石のような何かが沈んでいた。
数分後、ミヅキは席を立ち、千円札を一枚差し出す。
「……また来ても、いいですか?」
「もちろん。歓迎しますよ、うちの冷やしが復活するその日まで」
「約束ですよ」
ミヅキはそう言って、帽子をかぶり直すと、夏の日差しの中へと消えていった。
その背中は、どこか風のように儚かった。
ミヅキが去ったあと、信吾は厨房に戻りながら、湯気の立つ鍋を眺めていた。
さっきまで感じていた重石のような気持ちは、少しだけ軽くなっていた。
「……似てる。でも違う、か」
それは、最も厳しくも優しい評価だった。
(俺の味、か……)
そう呟いた時、ふと、先ほど見た父のレシピ帳の一文が頭をよぎった。
“冷たさは、心で作る。驚かせるな。包みこめ”
父はきっと、料理に“情”を込めていた。
誰かの心を包みこむように、静かに、丁寧に。
そのとき、再び黒電話が鳴った。
プルルルル……プルルルル……
今度は、少し躊躇いながらも、受話器を取る。
「はい、担々亭です」
「……ミヅキです。すみません、さっきのお礼を言い忘れて……」
「ああ、いや、わざわざありがとう」
「……やっぱり、あなたの声、懐かしい」
「え?」
「……あ、なんでもないです。じゃあ、また……」
またしても、すぐに通話は切られた。
しかしその声には、確かな安堵と、どこか含みのある響きがあった。
数日後。
ミヅキは週に二度ほど、担々亭に現れるようになった。
注文するのはいつも同じ、担々麵。
そして食べ終わると、短く何かを語り、静かに帰っていく。
「……この町って、音が柔らかいですね。風もそうだけど、車の音も、子どもの声も」
「ん、そうか? 宇都宮が静かなんじゃなくて、東京がうるさいだけかもな」
「そうかもしれませんね。でも、ここにいると、母が生きてた頃を思い出すんです。冷やし担々麵と……父のことを」
信吾の箸が止まった。
「……お父さんとは、会ってたのか?」
「いいえ。写真も見たことがありません。……母はずっと独りで私を育ててくれて、でも、ある日──“あの人は冷やし担々麵が得意だった”ってポツリと」
「……」
「私はそれを、まるで宝物のように覚えていて……だから探したんです、この店を」
信吾は、その場で何も言えなかった。
喉の奥がじんと痛み、まるで唐辛子が逆流したかのようだった。
夜、帳が落ちて、暖簾をしまったあと。
信吾はレシピ帳を再び開いた。
父の走り書きと汚れたページの隙間から、別の写真が滑り落ちた。
それは、若き父が、ある女性と仲睦まじい様子で写る一枚の写真だった。
ぼんやりとしたモノクロの中に、確かに写っているその女性の顔に、信吾は見覚えがあった。
「……まさか……」
その横顔は、ミヅキと瓜二つだった。
(……あの子の母さん……?)
冷やし担々麵を通して出会った、謎めいた女。
そして今、亡き父が遺した記録が語りはじめる。
ミヅキの正体は──
彼女がなぜ「懐かしい」と言ったのか、その理由が、じわじわと明らかになろうとしていた。
第三章 馬場、走り出す
宇都宮のはずれ、すっかり使われなくなった馬場家の旧倉庫。
その扉を開けたのは、十年以上ぶりだった。
鉄の蝶番は錆びてギィギィと不吉な音を立て、埃の匂いが顔を撫でる。
かつてこの場所には、父が“秘密基地”と呼んでいた作業場があった。
(あの写真のことを確かめないと……あれは本当に……)
信吾は思い立ったように、古びた書棚を漁った。
すると奥の段ボールから、例の女性──ミヅキの母と思しき人物と父が一緒に写る数枚のスナップが出てきた。
公園、縁日、そして……牧場。
父は、確かに彼女と一緒に一頭の馬を撫でていた。
(なぜ、馬なんだよ……親父……)
そして、その疑問は突如、現実の音として現れた。
ヒヒィーン……パカ……パカ……
「……え?」
まさか、と思いながら裏手に回ると、そこには──
馬がいた。
雑草に囲まれた空き地に、柵に繋がれた老馬が、のそのそと草を食んでいた。
目の周りは白く、毛並みはガサついており、どこからどう見ても競走馬のような気品はない。
だが、その背中にはなぜか誇りが宿っていた。
その名札には、こう記されていた。
名前:マルタ
性別:牡(おす)
年齢:推定26歳
(……マルタ?)
信吾は思い出す。
父がときおり、何かを語るときに使っていた名前だった。
「おい、マルタ、まだ生きてたのか……」
マルタは耳だけピクリと動かし、また黙々と草を食べた。
そして傍らのポストに貼られた、父の手書きメモが目に入った。
「担々のコシは、マルタの鼓動で作る」
――馬場善三
「……は?」
信吾は数秒間、意味が理解できずに固まった。
(コシを……馬の……鼓動で?)
バカじゃねえのか、と思った。
けれど父のことだ。本気で言っている。
数時間後。
信吾は、倉庫の中で粉をこね、麺を打ち始めていた。
近くでマルタが静かに見ている。
「ほら、動け。足踏みだ。リズム刻め」
マルタは、ほんの気まぐれのように前足をパカリと動かす。
そのタイミングに合わせて、信吾は足で練った麺の生地を踏み続ける。
パカッ、パカッ……
グッ、グッ……
「……なるほどな……鼓動だ」
彼はそのとき、初めて感じた。
父が言っていた「料理に生き物のリズムを取り入れろ」という意味を。
「バカみてぇだけど……なんか、おもしれぇじゃねぇか」
そして──
彼の中で、眠っていた“冷やし担々麵”への情熱が、静かに再燃しはじめていた。
マルタのゆったりとした足取りに合わせて、信吾は生地を踏み続けた。
倉庫の中に響くパカパカという馬の蹄の音と、自分の足のリズムが次第にシンクロしていく。
「そうか……このリズムで打つと、麺のコシが違うのか」
一心不乱に踏み込むたび、粉の塊が滑らかな生地に変わっていく。
信吾の頭に、父の声が蘇った。
「麺はただの麺じゃねぇ。鼓動だ。生きてるもんだ」
生地を伸ばし、切り分ける。
触ると冷たく感じるほど、こねたての生地は心なしか柔らかく、そして強靭だった。
「……やってみるか」
彼は厨房へ戻り、冷水で麺を締め始めた。
水の流れる音が、マルタの蹄のリズムと不思議な調和を見せている。
「……これだよ、親父」
スープを仕込み、肉味噌を温める。
そして、器に麺を盛り、上から胡麻だれをかける。
信吾は一度深呼吸をして、冷たい麺を口に運んだ。
──モチッ、プリッ、そしてスッと広がる冷たさと胡麻の香り。
「……ああ、これだ」
涙がぽろりとこぼれた。
「お前の味だよ、親父……」
そのとき、電話が鳴った。
今度は信吾の携帯だ。
画面に表示された番号は、見覚えのない番号だった。
躊躇いながらも、通話ボタンを押す。
「はい、馬場です」
「……信吾さん? 私です、ミヅキです」
「ああ、来てくれたのか」
「はい……そして、私、話があります。今から、行きます」
第四章 レシピの在処
ミヅキが担々亭に再び訪れたのは、春の終わり頃だった。
外の桜は散り始め、街には新緑の香りが漂っている。
「信吾さん……」
カウンター越しに差し出された手には、一冊の小さなノートが握られていた。
古びた革のカバーに金色の文字で「善三」と刻まれている。
「父さんの……レシピノート?」
「はい。これ、実は私の母が最後まで持っていたものです。亡くなる直前に、私に渡してくれました」
「そうか……」
信吾はそのノートを開いた。
中には父が書き残した数々のレシピや料理にまつわる思い出、そして手書きのメッセージが散りばめられていた。
だが、あるページだけが妙に厚みを持っていて、慎重にめくると、数枚の古い写真と一枚の手紙が挟まれていた。
写真には、父とミヅキの母、そして老馬マルタが一緒に写っている。
そして手紙にはこう記されていた。
「担々の命は麺にある。だが、その麺の命をつなぐのは鼓動だ。
それは馬の鼓動、そして人の鼓動。
このリズムを掴めた時、冷やし担々は蘇る」
-善三
信吾は呆然とした。
「……まさか、俺はまだ、半分しか知らなかったのか」
ミヅキは小さく微笑んだ。
「父さんは、料理だけじゃなくて、馬のことも愛していたんですね」
「そうだ。だが、俺は……マルタをほったらかしにしてた」
信吾は覚悟を決めて言った。
「よし、マルタを連れて街に出よう。俺たちでリズムを探すんだ」
それから数日後、信吾は倉庫からマルタを連れ出し、宇都宮の街をゆっくり歩き始めた。
街行く人は怪訝そうに見たが、信吾は気にしなかった。
「マルタ、俺たちの担々麵の命、見つけに行くぞ」
マルタを連れての街歩きは、思ったよりも多くの人々の目を引いた。
老馬と中年の男がのんびりと商店街を進む姿は、どこか奇妙でありながらもどこか温かみを感じさせる光景だった。
「馬場さん!久しぶり!」
突然、元料理人の老人が声をかけてきた。
「おお、元気だったか。昔の担々亭の味は、まだ忘れてねえよ」
信吾は軽く会釈しながら答えた。
「実はさ、今また冷やし担々麵を復活させようと思ってるんだ」
老人は目を細めて言った。
「そうかい、それは嬉しい話だ。あの味はなぁ……秘訣は、麺を冷やす“水”の温度と冷やし方だと思うんだ」
「水の温度……?」
「そう。うちの店では、氷水でキンキンに冷やすのが基本だが、父さんはそれだけじゃなかった。冷やし方に“リズム”があった」
「リズム……」
信吾はふと思い出す。
父の言葉と、マルタの蹄の音。
その日、商店街のイベントで、昔の料理仲間やお客さんたちが集まった。
「そうだ、担々祭りをやろうじゃねえか!」
ある常連客が声を上げた。
「担々麵をテーマにした祭りだ!」
信吾は胸の奥に熱いものを感じた。
これこそ、父の想いを受け継ぐチャンスかもしれない。
マルタはゆっくりと、だが確かな鼓動を刻みながら、信吾のそばを歩いていた。
第五章 担々祭り、始まる
夏の気配が色濃くなる頃、宇都宮の街では「担々祭り」が盛大に開催された。
商店街のアーケードには赤と黄色の提灯が揺れ、屋台の匂いが漂う。
信吾はマルタとともに店の前に立っていた。
彼の顔には、どこか達成感と緊張が入り混じっていた。
「今年の冷やし担々麵は、今までとは違う。リズムを、心を込めた味だ」
そう言いながら、厨房で最後の仕込みを進める。
祭りの開始と同時に、多くの人々が担々亭に集まった。
懐かしい顔もあり、新しい客もいる。
「冷やし担々麵、待ってました!」と声が飛ぶ。
信吾はその声に応えるように、一杯一杯を丁寧に作り続けた。
マルタも祭りの賑わいに馴染みながら、時折蹄でリズムを刻んでいた。
その時──
「信吾さん!」と叫ぶ声がした。
振り向くと、ミヅキが帽子を脱ぎ、笑顔で手を振っている。
「来たよ、待っててくれた?」
信吾は力強く頷いた。
「おう、みんなのために、最高の冷やし担々を作るぞ!」
祭りは盛り上がり、冷やし担々麵は瞬く間に評判を呼んだ。
人々の笑顔と笑い声が、暑さを忘れさせるほどだった。
しかし、祭りの終わりに、思いもよらぬ出来事が信吾を待ち受けていた。
祭りの終盤、信吾は冷やし担々麵の最後の一杯を作り終え、汗だくのまま外に出た。
夜空には提灯の灯りがぼんやりと揺れている。
そこに、見知らぬ男が現れた。
「お前が、馬場信吾か」
低くて冷たい声。
信吾は咄嗟に身構えた。
「あなたは……?」
「俺は……お前の父親の昔の友人だ」
男の名は渡辺昭二。かつて父と共に担々麵の味を追求していた仲間だったが、ある理由で疎遠になっていた。
「父さんが残したレシピと、写真の女性について、話がある」
信吾は戸惑いながらも、男の話に耳を傾けた。
渡辺は語った。
「その女性は、お前の父さんの昔の恋人だ。お前のことを知らずに死んだが……」
「俺のこと?」
「お前が知らない真実がある。お前が本当の馬場家の血を引く者だと」
信吾は混乱した。だが、その話はさらに続いた。
「父は、最後にお前に伝えたかったことがあった。真実をな」
男は古い封筒を取り出し、中から一通の手紙と古い写真を差し出した。
「読んでみろ」
信吾は震える手で手紙を開いた。
そこには、父・善三の筆跡でこう書かれていた。
『信吾へ。お前の母は実は……私の妻ではなかった。だが、お前は私の息子だ。
そして、真実はもっと深い。ミヅキもまた、お前の娘だ。彼女は母が遺した最後の贈り物だ。
すべては、お前が本当の家族を見つけるための試練だ。』
信吾は目の前が真っ暗になった。
「娘……ミヅキが……?」
そのとき、祭りの音楽が遠くから聞こえてきた。
最終章 ──家族のリズム
冷やし担々麵を囲んで再会した家族。
信吾とミヅキ、そして渡辺とマルタ。
すべての点が線となり、やっと一本の物語が繋がった。
馬場家の秘密と情熱は、味に宿り、人々の心を繋いだ。
「冷たさは、心で作る」
父の言葉を胸に、信吾は新たな一歩を踏み出した。
【終わり】
最後まで読んでいただきありがとうございました🤗
今後とも「ロジテルネット」並びに ロジテル伊藤をよろしくお願いいたします✋🥺
—————————————————————————————————————————————-
現在ロジテルでは、私たちとともに はたらく配車スタッフを募集しております。
・ 本社(栃木県宇都宮市) TEL:028-333-5353
・ 仙台営業所(宮城県仙台市青葉区) TEL:022-796-9450
・ 名古屋営業所(愛知県名古屋市中村区) TEL:052-756-3830
本社、営業所とも20代、30代の男性、女性が活躍しています。ぜひお問合せください。